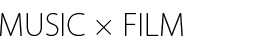
![]()
『NOISE』
上原輝樹

2005年6月、フランスの地方都市サン=ブリューで1983年から毎年開かれてきた「アート・ロック・フェスティヴァル」の「白紙委任状」を託されたオリヴィエ・アサイヤスは、華麗なる友人の面々と"同志"とも言うべき仲間たちを総動員し、ライブ演奏、ポエトリーリーディング、実験映画を織り交ぜた多彩なプログラムによる、"音楽"と"映像"が対話する刺激的な磁場を創り出した。この3日間に渡るフェスティヴァルの模様が映画『NOISE』に結実、夏フェスひしめく東京の夏の夜に堂々"爆音上映"される運びとなった。
「フェスティヴァルを観客として楽しむのは論外、ただ単に断片や全体を撮影するのではなく、何らかの方法で自分がコンサートに参加しなければ無意味だ」と考えたアサイヤスは、"アサイヤス王国"の撮影監督エリック・ゴーティエに同行を求め、『デーモンラヴァー』(2002)のサウンド編集を務めた、ソニック・ユースの仕事に馴染みのあるオリヴィエ・ゴワナールにコンサートを録音する責務を任せる。その為に、2台の移動スタジオを設置、映画『NOISE』で"映像"と"音楽"の融合を実現するためには欠かせない重要な素材を、最良のコンディションで確保するべく最大限の努力が為されることになった。そもそも、このプロジェクト自体がアサイヤスにとっては喜びであり、こうして"参加"することで余計な苦役を呼び込まないよう、撮影は幾人かの信頼のおける映像作家が即興で行い、問題が出ればその場で解決していくという方法が採用されることになった。事前に綿密な計画を立てることで見えてきてしまう、対処しなければならないであろう諸問題はさておき、イベント当日にパフォーマー達と同レベルのテンションで挑もうという、アサイヤスの大胆な試みには、"演出家"としての骨太なスマートさを感じさせられる。こうした準備を経て、フェスティヴァルはいよいよ始まる。

もちろん、フェスティヴァルのプログラムもアサイヤスがディレクションしている。"アサイヤス王国"の女優たち(ジャンヌ・バリバール、マリー・モディアノ、ホワイト・タヒナのジョアンナ・プレイスら)の艶やかなライブパフォーマンスを、映画の進行上、真ん中で真空管のように繋いでいる、アフェル・ボクームのマリのブルースは、西洋音楽の構造から見れば明らかに"異端"、故に、ノイズ・ミュージックの王道を往くかのように螺旋を描いて精神の高みへ上昇して行くアコースティックな近無限ループは、この空間に違和感無く収まっている。そういう意味では、やはりニューヨーク・アンダーグラウンドの帝王ソニック・ユースのメンバーを中心に形成された、ミラー/ダッシュ(サーストン・ムーア&キム・ゴードン)とテクスト・オブ・ライト(リー・ラナルド、スティーブ・シェリー、アラン・リクト、ウルリヒ・クリーガー、ティム・バーンズ)の弾けっぷりが圧巻だ。中でも、ミラー/ダッシュのパフォーマンスは、実際のステージは90分にも及び、彼らのベストパフォーマンスだったと、ジム・オルークは証言している。その片鱗は本作で充分堪能することができる。

尤も個人的には、アサイヤス映画の才能豊かな美しい女優たちのパフォーマンスに大いに目と耳を奪われた事を告白しておく。哲学者を父に物理学者を母に持つ、エリート校出身の才女、ジャンヌ・バリバールは、アサイヤスの『8月の終わり、9月の初め』(1998)でスペインのサン・セバスチャン映画祭最優秀女優賞を獲得、ジャック・リヴェットの『恋ごころ』(2001)『ランジェ公爵夫人』(2007)など、女優としての評価もさることながら、ソロアルバムを2作ものにし、ドスの効いた重い歌唱をメランコリーに輝かせる。昨今の『サガン -悲しみよこんにちは-』(2008)やアサイヤスの『クリーン』(2004)では、いずれもレズビアンの役柄で異彩を放っていたが、ペドロ・コスタが撮影したという日本でのライブ映像(※)も本作と共に秘かに楽しみたいところ。そして、素晴らしいライブパフォーマンスが、『クリーン』冒頭でモンタージュされたメトリックが『NOISE』のラストを飾る。クラッシュのポール・シムノンを想起させるゴリゴリベースが炸裂する70年代ロンドンパンクと80年代ニューウエィブPOPが融合したサウンド、そして何と言っても、ボーカル&シンセサイザーのエミリー・ヘインズのクールネスとその裏腹の扇情的なライブパフォーマンスが唯一無比の魅力を放つメトリックの素晴らしいパフォーマンスを体験する頃には、誰もが頭の中が真っ白になっていることだろう。この脳味噌の"真空状態"こそが、サン=ブリューの会場でも共有された"NOISE"なのではなかったか。

音楽映画としては、シュナーベルの傑作『ルー・リード/ベルリン』以来の素晴らしい音楽映画体験だったが、このノイズ・ミュージックの系譜を遡っていけば、そこには、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「White Light / White Heat」(1969)という偉大なる金字塔があることを想起さずにはいられない。思えば、初期ヴェルヴェッツのパトロンであり、1960年代のニューヨークでアーチストやミュージシャン、女優、ドラッグクイーン、ジャンキーといったニューヨークのワイルドサイドの住人たちを「ファクトリー」に集めて、「マルチメディア・ショー」を繰り広げていたアンディ・ウォホールが、その当時熱を上げていたのが、他ならぬ"映画"作りであったわけで、時空を超えて、フランスの一地方のフェスティヴァルで似たような役回りを務め、これをフィルムに収めたアサイヤスの行いは、そこにニューヨーク・アンダーグラウンド・カルチャーの後継者ソニック・ユースがいるということが明らかに重要なのだが、実に正統的にノイズ・ミュージックの継承を手助けし、この模様をフィルムという媒体に定着させているという印象を受ける。アサイヤスという映画作家は、『感傷的な運命』や『夏時間の庭』で、過去の時代の価値観の現代的な継承の作法を映画の中心的なテーマに据えてきたが、一見毛色が違って見える『NOISE』でさえ、実に律儀に過去の遺産を現代的なマナーで継承していく誠実な映画作家の姿が見えてくる。正に「作家とは自らの精神的種族の保存の為に働くもの」(河野多恵子)に違いない。
ところで、今回の"爆音上映"、映画『NOISE』の"音楽"を規格外の"爆音"で体感できる贅沢な機会なのだが、監督のアサイヤスにしても、まさか自分の作品が、わざわざ"映像"と"音"のバランスを逆転させるという倒錯的な環境で上映されるとは思ってもみなかったことだろう。<ソニマージュ>を提唱したゴダールにしても、"映像"と"音楽"の融合を試みるアサイヤスにしても、"映像"と"音"を同レベルに併置しようと試みたのであって、これを逆転させようとしたわけではない。こんなマニアックな試みは、日本に住む者だけが体験することが出来る、素晴らしく馬鹿げた特権なのかもしれない。
『NOISE』
7月11日(土)より、
吉祥寺バウスシアターにて3週間限定爆音レイトショー!
監督:オリヴィエ・アサイヤス
出演:ミラー/ダッシュ(キム・ゴードン、サーストン・ムーア)、ジャンヌ・バリバール、メトリック、テクスト・オヴ・ライト(リー・ラナルド、スティーヴ・シェリー、アラン・リクト、ウルリヒ・クリーガー、ティム・バーンズ)、アフェル・ボクーム、マリー・モディアノ、アラ、ホワイト・タヒナ(ジョアンナ・プレイス、ヴァンサン・エプレー)、ル・デビュ・ドゥ・ラ(パスカル・ランベール、ケイト・モラン)
編集:リュック・バルニエ、マリオン・モニエ
録音:オリヴィエ・ゴワナール、ジャン=バチスト・ブリュヌ、ニコラ・カンタン
撮影:ミカエル・アルメレイダ、オリヴィエ・アサイヤス、エリック・ゴティエ、レオ・インスタン、ロラン・ペラン、オリヴィエ・トレス
2005年/フランス/120分/ヴィスタサイズ
© association wild rose • aresenal associes 2005
提供:キングレコード、boid
配給:boid+iae
『NOISE』
オフィシャルサイト
http://www.noise-bb.jp/
 「オリヴィエ・アサイヤス特集」
「オリヴィエ・アサイヤス特集」
 『夏時間の庭』レビュー
『夏時間の庭』レビュー
 『感傷的な運命』レビュー
『感傷的な運命』レビュー
 『クリーン』レビュー
『クリーン』レビュー
 アサイヤス監督『夏時間の庭』
アサイヤス監督『夏時間の庭』
インタヴュー
 アサイヤス監督
アサイヤス監督
『クリーン』『NOISE』インタヴュー

※ペドロ・コスタDVD-BOX(血/溶岩の家/骨)に収録
7月11日(土)より、
吉祥寺バウスシアターにて3週間限定爆音レイトショー!
監督:オリヴィエ・アサイヤス
出演:ミラー/ダッシュ(キム・ゴードン、サーストン・ムーア)、ジャンヌ・バリバール、メトリック、テクスト・オヴ・ライト(リー・ラナルド、スティーヴ・シェリー、アラン・リクト、ウルリヒ・クリーガー、ティム・バーンズ)、アフェル・ボクーム、マリー・モディアノ、アラ、ホワイト・タヒナ(ジョアンナ・プレイス、ヴァンサン・エプレー)、ル・デビュ・ドゥ・ラ(パスカル・ランベール、ケイト・モラン)
編集:リュック・バルニエ、マリオン・モニエ
録音:オリヴィエ・ゴワナール、ジャン=バチスト・ブリュヌ、ニコラ・カンタン
撮影:ミカエル・アルメレイダ、オリヴィエ・アサイヤス、エリック・ゴティエ、レオ・インスタン、ロラン・ペラン、オリヴィエ・トレス
2005年/フランス/120分/ヴィスタサイズ
© association wild rose • aresenal associes 2005
提供:キングレコード、boid
配給:boid+iae
『NOISE』
オフィシャルサイト
http://www.noise-bb.jp/
インタヴュー
『クリーン』『NOISE』インタヴュー
※ペドロ・コスタDVD-BOX(血/溶岩の家/骨)に収録
Comment(0)