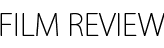
![]()
『セントアンナの奇跡』
上原輝樹

"映画を作れるカシアス・クレイ(モハメド・アリ)"、"黒人のウディ・アレン"といった数々の異名を持つ"ポスト・ソウル"世代(※)の鬼才スパイク・リーが、比較的小柄な体躯からスイングする度にヘヴィー級のパンチを繰り出しきたことは、ここ数年の作品(『25時』(2002)、『セレブの種』(2004)、『インサイド・マン』(2006))を想起するだけでも充分だが、さらにもう10年遡れば、『クロッカーズ』(1995)、『ゲット・オン・ザ・バス』(1996)、『サマー・オブ・サム』(1999)といった傑作群を生み出し、既に成熟しつつあった映画作家の姿を見出せるであろうし、もう更に10年遡れば、『シーズ・ガッタ・ハヴ・イット』(1985)、『ドゥー・ザ・ライト・シング』(1989)といったアメリカ国内で大いに物議を醸した、従来のステレオタイプに収まらない"新しい黒人像"を戦闘モードで提示してみせた中産階級出身の若き武闘派の姿を鮮烈に思い描くことができるだろう。
映画は、TV画面で『史上最大の作戦』(1962)を観ながら男が「私たちも闘ったのだ」と呟やくシーンから始まる。『史上最大の作戦』は、第2次世界大戦中に行われた連合軍によるノルマンディーへの史上最大規模の上陸作戦を描き、国際的な豪華キャストが多数出演した大作映画だ。史実では、この上陸作戦には1700名余りの黒人兵が従軍していたことが明らかにされているのだが、映画では一人も黒人兵が描かれておらず、1963年に全国有色人種向上協会(NAACP)は、『史上最大の作戦』はハリウッドスタジオの人種差別主義の好例だとして、映画会社に対して訴えを起こしている。もっともこの上陸作戦には300万人近い兵員が動員されており、その内の1700人を映画で描けるかどうかは議論の余地が残るところだが、このことを踏まえた上で、「私たちも闘ったのだ」という呟きを聞けば、スパイクがなぜ黒人兵部隊"バッファロー・ソルジャー"の物語を映画化しようと思ったのか、その理由は明らかだろう。
映画の舞台は、1983年のニューヨーク、郵便局で局員が窓口に来た男の顔を見るなり射殺するという不可解な事件が起きる。スパイク映画の常連ジョン・タトゥーロがこの事件を調べる刑事を演じ、短い出番ながらも印象的な存在感で観客を惹き付ける。射殺犯は定年退職を3ヶ月先に控えた品行方正な郵便局員だったのだが、この男の自宅からは、闇市場で500万ドルはするという歴史的な彫像の頭部が発見される。そして、映画の冒頭にこの男(ヘクター)が呟いた「私たちも闘ったのだ」という言葉も観客の耳に残っているはずだ。深まりゆく謎を解くには、この彫像の頭部が行方不明になった1944年のイタリアまで遡らなければならない。

映画の舞台は、1944年のイタリア、トスカーナへ移る。若き日のヘクターは、 "バッファロー・ソルジャー"の一員として、ナチスドイツ軍との激しい闘いに身を投じていた。ヘクターを含むバッファロー・ソルジャーの一隊が進むセルキオ川流域の戦場には、ナチスによる心理戦が仕組まれている。「黒人のあなたたちがなぜ白人の戦争のために命をささげるの?祖国に帰りなさい!奴隷たちよ!」という戦意を挫くような言葉がセクシーな声で、スパイクお得意の小道具"拡声器"を通して流れてくる。声の主は、アレキサンドラ・マリア・ララが演じる"アクシス・サリー"、ラジオを通して兵士のモラルに揺さぶりをかけた"東京ローズ"のナチス版で、実在した人物をモデルにしている。『コッポラの胡蝶の夢』の時とは全く別人の顔を見せてくれる、ビッチーなアレキサンドラ・マリア・ララが素晴らしい。美しい川面が揺れ、アレキサンドラ・マリア・ララのセクシーなヴォイスが画面を支配する中、突如セルキオ川に閃光が走る。ナチスドイツ軍の一斉射撃により、バッファロー・ソルジャーの一隊は無惨にもそのほとんどが殺されてしまう。
この局面を生き延びた4人のバッファロー・ソルジャーは、ドイツ兵の目を逃れ、トスカーナの村に迷い込む道すがら、不思議な少年を助ける羽目になる。この少年は、普通の人には見えないものが見えたり、壊れた無線も直してしまう神秘的な力を持っている。少年の登場を契機に、映画は幾分ファンタジックな様相を呈するのだが、この少年の存在こそが凄惨な戦場に於いても映画のタイトルになっている"奇跡"をのちに呼び込むことを観客に期待させながら物語は更なる展開を見せる。

バッファロー・ソルジャーと少年は、英語を話す美しい聡明なイタリア女性レナータ(ヴァレンティナ・チェルヴィ)に出会う。レナータの置かれた状況には、当時のイタリア社会の混乱が凝縮されている。レナータの父は、ムッソリーニを信奉するファシストであり、友人はナチスドイツに抵抗するパルチザンのメンバー、そこにアメリカからやってきたバッファロー・ソルジャーの面々が加わり、レナータの家は『ドゥー・ザ・ライト・シング』のブルックリンのピザショップさながらの一触即発ムードが漂う中、スパイク一流の人種間や内輪の人間同士の軋轢がリアルに描かれる。ここで交わされる活き活きした会話の数々はスパイク映画ならではのリズム感に溢れ、ニューヨーク饒舌系映画作家の真骨頂が表れている。明らかにネオレアリズモ映画を目指した本作のイタリアにおけるロケーションや衣装、人々の描写の見事さは、ネオレアリズモ直系の巨匠エルマンノ・オルミ作品の製作や、ナンニ・モレッティの映画を配給した経験を持つ二人のイタリア人プロデューサ(ロベルト・チクット、ルイジ・ムジーニ)の存在が成功の鍵を握っていたに違いないが、この人脈に辿り着くところが、シネフィルのスパイク・リーならではの勘の良さだろうか。

映画は、パルチザンの登場と共に、雲風急を告げる。"セントアンナの大虐殺"の秘密に関連してナチスドイツが血眼で追っている脱走兵はパルチザンによって捕らえられ、トスカーナ山村の隠れ家"レナータの家"に捕虜として確保されていた。だが、その居所がある裏切りによってナチスドイツに知られてしまい、村は報復の砲火を浴び殲滅的な殺戮が行われる。物語は、登場人物すべての運命を巻き込んで壮大な悲劇へと様変わりしていく。"セントアンナの大虐殺"や"バッファロー・ソルジャー"といった史実に基づいた物語を饒舌に語るだけでなく、最も映画的に困難な試み"奇跡"を描くというスパイクの野心が果たして成功しているのか否かは、映画館に足を運んで自らの目で確かめてほしい。もっとも、その野心の正否に関わらず、本年度最大に涙腺が緩む一作となっていることは間違いない。
『セントアンナの奇跡』
Miracle at St. Anna
7月25日(土)、TOHOシネマズ シャンテ、テアトルタイムズスクエア他にて全国ロードショー
監督:スパイク・リー
原作・脚本:ジェームズ・マクブライド(原作本「Miracle at St. Anna」)
製作:ロベルト・チクット、ルイジ・ムジーニ、スパイク・リー
製作総指揮:マルコ・ヴァレリオ・プジーニ、ジョン・キリク
撮影:マシュー・リバティーク、A.S.C.
美術:トニーノ・ゼッラ
編集:バリー・アレクサンダー・ブラウン
衣装:カルロ・ポッジョリ
音楽:テレンス・ブランチャード
出演:デレク・ルーク、マイケル・イーリー、ラズ・アロンソ、オマー・ベンソン・ミラー、マッテオ・シャボルディ、ルイジ・ロ・カーショ、レオナルド・ボルツォナスカ、ヴァレンティナ・チェルヴィ、ピエルフランチェスコ・ファヴィーノ、セルジオ・アルベッリ、オメロ・アントヌッティ、リディア・ビオンディ、ウォルトン・ゴギンズ、トリー・キトルズ、D・B・スウィーニー、ロパート・ジョン・バーク、ヤン・ポール、アレクサンドラ・マリア・ララ、クリスチャン・ベルケル、ケリー・ワシントン、リーランド・ガント、ジョセフ・ゴードン=レヴィット、ジョン・タトゥーロ、ジョン・レグイザモ
2008年/アメリカ・イタリア/英語・イタリア語・ドイツ語/カラー/スコープサイズ/DTS・SRD・SR/163分
配給:ショウゲート
写真:© 2008 (Buffalo Soldiers and On My Own Produzione Cinematografiche)- All Rights Reserved.
『セントアンナの奇跡』
オフィシャルサイト
http://www.stanna-kiseki.jp/
 スパイク・リー監督インタヴュー
スパイク・リー監督インタヴュー
※"ポスト・ソウル"世代
名著「リズム&ブルースの死」や「ヒップホップ・アメリカ」、「マイケル・ジャクソンのすべて」などの著書で知られる作家・批評家のネルソン・ジョージが、自身の2001年の論文集の書名に「ポスト・ソウル」という言葉を初めて使ったとされている。ネルソン・ジョージは、"ポスト・ソウル"世代を、1963年3月のワシントン大行進(公民権運動のエピック)から、1978年のバッキー訴訟事件(黒人の中産階級化が進み、少数民族を優先的に入学させる優遇措置はもはや違憲とした判決)のあいだに生まれた黒人、と定義している。
1960年代に頂点を迎えた"ソウル"世代の後の1980年代以降の"ポスト・ソウル"世代は、"ソウル"世代の様々な闘いを通して地位を向上させた黒人社会が新たな段階に入ったとされ、その新たな"黒人像"を鮮烈に提示することに成功した世代とされている。スパイク・リーはこの世代を最も明確に代表するアーチストの一人とみなされ、その定義に従えば、"ポスト・ソウル"世代には、つい先日急逝した"キング・オブ・ポップス"マイケル・ジャクソンはもちろん、カニエ・ウエストやジャン=ミシェル・バスキア、キャラ・ウォーカーといったアーチスト、そしてバラク・オバマ大統領もこの世代に属することになる。
"ポスト・ソウル"については、『水声通信』2009年3/4月号「特集:ポスト・ソウルの黒人文化」に詳しい研究が掲載されている。
Miracle at St. Anna
7月25日(土)、TOHOシネマズ シャンテ、テアトルタイムズスクエア他にて全国ロードショー
監督:スパイク・リー
原作・脚本:ジェームズ・マクブライド(原作本「Miracle at St. Anna」)
製作:ロベルト・チクット、ルイジ・ムジーニ、スパイク・リー
製作総指揮:マルコ・ヴァレリオ・プジーニ、ジョン・キリク
撮影:マシュー・リバティーク、A.S.C.
美術:トニーノ・ゼッラ
編集:バリー・アレクサンダー・ブラウン
衣装:カルロ・ポッジョリ
音楽:テレンス・ブランチャード
出演:デレク・ルーク、マイケル・イーリー、ラズ・アロンソ、オマー・ベンソン・ミラー、マッテオ・シャボルディ、ルイジ・ロ・カーショ、レオナルド・ボルツォナスカ、ヴァレンティナ・チェルヴィ、ピエルフランチェスコ・ファヴィーノ、セルジオ・アルベッリ、オメロ・アントヌッティ、リディア・ビオンディ、ウォルトン・ゴギンズ、トリー・キトルズ、D・B・スウィーニー、ロパート・ジョン・バーク、ヤン・ポール、アレクサンドラ・マリア・ララ、クリスチャン・ベルケル、ケリー・ワシントン、リーランド・ガント、ジョセフ・ゴードン=レヴィット、ジョン・タトゥーロ、ジョン・レグイザモ
2008年/アメリカ・イタリア/英語・イタリア語・ドイツ語/カラー/スコープサイズ/DTS・SRD・SR/163分
配給:ショウゲート
写真:© 2008 (Buffalo Soldiers and On My Own Produzione Cinematografiche)- All Rights Reserved.
『セントアンナの奇跡』
オフィシャルサイト
http://www.stanna-kiseki.jp/
※"ポスト・ソウル"世代
名著「リズム&ブルースの死」や「ヒップホップ・アメリカ」、「マイケル・ジャクソンのすべて」などの著書で知られる作家・批評家のネルソン・ジョージが、自身の2001年の論文集の書名に「ポスト・ソウル」という言葉を初めて使ったとされている。ネルソン・ジョージは、"ポスト・ソウル"世代を、1963年3月のワシントン大行進(公民権運動のエピック)から、1978年のバッキー訴訟事件(黒人の中産階級化が進み、少数民族を優先的に入学させる優遇措置はもはや違憲とした判決)のあいだに生まれた黒人、と定義している。
1960年代に頂点を迎えた"ソウル"世代の後の1980年代以降の"ポスト・ソウル"世代は、"ソウル"世代の様々な闘いを通して地位を向上させた黒人社会が新たな段階に入ったとされ、その新たな"黒人像"を鮮烈に提示することに成功した世代とされている。スパイク・リーはこの世代を最も明確に代表するアーチストの一人とみなされ、その定義に従えば、"ポスト・ソウル"世代には、つい先日急逝した"キング・オブ・ポップス"マイケル・ジャクソンはもちろん、カニエ・ウエストやジャン=ミシェル・バスキア、キャラ・ウォーカーといったアーチスト、そしてバラク・オバマ大統領もこの世代に属することになる。
"ポスト・ソウル"については、『水声通信』2009年3/4月号「特集:ポスト・ソウルの黒人文化」に詳しい研究が掲載されている。
Comment(0)