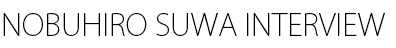
|
5. あってはいけないことが映画の中ではあちこちで起きる、 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Q:ラストシーンのジャン=ピエール・レオーの顔が忘れられないのですが、あそこに描かれてるのって私達が通常感じている死に対して抗うっていう感じではなくて、到来してくる死を待ちながらもじっと睨みつけるように凝視すると言いますか、その感じがすごく新しいなって思ったんです。それは監督ご自身の死生観のようなものに通じますか?
諏訪敦彦:僕はね、まだ死生観までは至ってないかもしれないですね。でもあの最後のショットっていうのは、死んでるのか寝てるのか分からないっていうような状況でシナリオには想定されてたんです。色々撮影しても上手くいかなくて、色々やってみたんだけど最後にジャン=ピエールに好きにやってくださいって、自分が思うように演じてくださいっていう風にして撮ったショットがあのショットなんです。本当に好きなようにやるよとか言ってやったんですけど、そのあと編集で切りましたけど、実はあの後、彼は死ぬんです。
Q:死ぬ身振りをしたっていうことですか?
諏訪敦彦:したんですよ、その身振りがものすごい勢いで、これ死んだようには絶対見えない(笑)、スタッフ一同みんな唖然としたんです、でも好きにやっていいよって言ったんだから次はないですよね、OKするしかない。それを使うっていう手もなくはなかったと思うんですけど、あまりにも元気いいので(笑)。ただやっぱりあの表情っていうかね、今おっしゃったみたいに、あの表情の強さっていうのを活かすっていう、それで映画を閉じようと思ったんです。ただ僕の死生観かどうかは別にして、僕とジャン=ピエールが話していたのは、今回の映画のテーマっていうのは、やっぱり生きることは素晴らしい、こういう風にしたいっていう、割と軽いノリでそういう話はしてたんです。彼は最近お坊さんマニアで、アジアに来ると必ずお坊さんに会う、それでそういう話が好きなんですよね。アルベルト・セラのこともあって死を演じることとか、死っていうことについて割と話しますけれども、暗い話はしたくないんですね彼も、それは凄く感じました。なぜかというと彼はそっちに引っ張られて落ちちゃう可能性が常にあるから、精神的に。悪い方に落ちちゃうと多分這い上がって来るのが大変なんだと思うんですよ、まあ病院に入ってたこともある人ですから。だから出来るだけ明るい話をしたいんだっていうのが彼の防衛本能としてあって、今回すごく明るい映画になってると自分でも思います。自分もそうですけど、弱い状態とか危機的な状況とか病気をしたりとか、そういうことを通過した人にとっては、やっぱり暗くなりたくないわけですよ、少しでも明るくいたい、なぜなら生きてることを実感できるのは生きてるのが辛いと思う時期があるから、そういうものを求めるわけでね。僕の映画はあんまり明るい題材を扱ってこなかったけど、そういう意味でいうと、今はより暗い、より辛い、より厳しい、世界的にもそういう状況だと思うし、個人的にもそういうこともある、ジャン=ピエールにとっては長い間そういう時期があったと思う、だから結果的に楽しい映画にしたかった。彼の前であんまり深刻な話はできないですから。
Q:ジャン=ピエールさんが子どもの映画を観て、美しく単純だって言ってるのがすごく印象に残ってるんです。あと監督が別世界っていう風におっしゃっていた、別世界に入っていく、例えば鏡とか、暗い門をくぐるとか、そういうものもすごく印象に残っていて、今おっしゃったこととちょっと似ちゃうかもしれないんですが、映画がそういうものを提示していくことで、どういうものであってほしいと思っていますか、観客に対して。
諏訪敦彦:最近、上映前によく言うのは、子どもみたいに観てほしい、子どもの悪ふざけみたいなもんだと思ってほしいっていうか(笑)。なんでこうなってるの、どういう人間でどういう繋がりがあって、ライオンってどういう意味なのっていう感じで、納得したり理解しようと思いたがるわけですね僕達は。例えば現代美術とか観てもこれ何なんだろう、どういう意味があるんだろうとかって解説読んだりして、そうか、なるほどとか思って安心したいわけですけど、子どもが遊んでる状態っていうのは別に何かをしたいわけじゃない、やってること自体が面白いからやってるのであって、それを見てることが面白ければいい、子どもの遊びっていうのは目的も意味もない、そういう時間の豊かさっていうのがある、だからそういう時間であってほしいって今回は思ってるんですよ。先日、フランスの試写会で、子どもだけの試写会をやったんです、200人くらいで。すっごいノリノリで観てましたよ、結構子どもも楽しむんだなと思いましたね。
Q:どういうところでノリノリになってるんですか?
諏訪敦彦:いちいち笑ってたし、フェードアウトする度に拍手が湧きました。映画が終わったらみんなで大合唱、だから結構面白いんじゃんと思って、幽霊とかライオンも出てきていいよみたいな、そういうのは僕はある意味でカーニバルであってほしいと思ってて。文芸評論家のバフチンがドストエフスキーの小説の形式はカーニバルなのだっていうことを言ってて面白いなって思って、なんでドストエフスキーはカーニバルなんだろうって思ったけど、カーニバルっていうのは演じるものも演じられるものも区別もなく、観客と舞台の区別もなく、鑑賞されるようなものでもなく生きられるものなんだと、だからカーニバルっていうのはいつどこで始まるか分かんないし、道端で誰か何か始めたら、それを見ていた通行人が何かを始めてもいいみたいな状態が作り出されていく、それを統御する作家みたいのがいないわけです。カーニバルでは、僕達が普段暮らしてる時にやってはいけないことをやっていいんです。ヒエラルキーとかが破壊されて、普段はやってはいけないっていうことをやってもいい、この子達がおじいさんをクソジジイとか言ってもいい。無作法であったり、無礼であるっていうことは、カーニバルにおいては有効なことで、しかもそこには普段いてはいけない幽霊がいるとか、ライオンもついでに通っちゃうとか。この映画の中ではジュールのお母さんが“現実”の地平を生きていますが、そこにおいてはあってはいけないことなんです。全部あってはいけないことが映画の中ではあちこちで起きる、そういうカーニバルのようなものであってほしい、だからジャン=ピエールが言うようにしかめっ面をして真面目に映画を作る人もいるけど、楽しみのために映画を作る人達もいる。それで、あのあと彼は延々とハワード・ホークスの『ハタリ!』(62)について語り出したんですけど、編集で切りました、さすがに(笑)。だからそういう風に観てほしいなって、今回は思っています。
| ←前ページ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 次ページ→ | |
