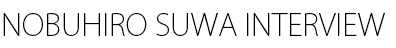
|
3. ジャン=ピエール・レオーは、現実を再現しようとは思ってない、 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Q:監督は、釜山映画祭の時にヌーヴェルヴァーグの話をされて、ヌーヴェルヴァーグの映画を観た時に、自分も作っていいんだって許可されたような気持ちになったという話をされましたね。今回ジャン=ピエール・レオーさんが出ていますが、彼の作品でどの作品が最高かは選べないとおっしゃっていましたが、この人と映画を撮りたいと思わされた場面があれば教えてください。
諏訪敦彦:はっきり覚えてないんですけど、ジャン=ピエール・レオーの何を最初に観たかといえば、『大人は判ってくれない』(59)ではないと思うんです。最初に、一番印象に強く残ったのは『男性・女性』(66)。トリュフォーのドワネルものが多分日本でちゃんと観れたのは、“ぴあ”でトリュフォー全作品上映があった時だから、多分『家庭』(70)とかは観れてない。『逃げ去る恋』(79)とか『家庭』とか、ちゃんと公開されてないんじゃないですかね。どの映画も、フランスでもそんなに成功した映画ってないんですよね、観客動員的には。同時代で多分最初に観たのは『アメリカの夜』(73)ですけど、その時にジャン=ピエール・レオーを特に強く意識したわけではなかったと思うんですよ、高校生だった時。初めて自分に印象を残したのは『男性・女性』、そして『中国女』(67)、ちょっと破壊的になっていきつつあるゴダール作品の中で、必死に演じてるジャン=ピエール・レオーですね。『男性・女性』の現場ルポルタージュが後で出版されて、「きちがいゴダール」っていうタイトルで翻訳されて、原題は「ゴダールを待ちながら」。『男性・女性』の現場ルポなんですけど、今みたいにメイキングビデオとかYoutubeとかないじゃないですか、映画も何回も観れないし。その本っていうのが、撮影の現場のムードをものすごく伝えてるんです、半分フィクションなんですけど、半分はルポ。ゴダールがこうやって現場に来て、ああしてこうして、なんか凄くムードの悪い現場で、カリカリしてて、カメラマンとゴダールが上手くいってないとか、スタッフは怒られるとか、その中でジャン=ピエール・レオーは右往左往してるみたいな。でも朝まで地下鉄のホームでゴダールは台詞書いてるとか、こうやって映画作ってるのかみたいなのを、ありありと感じることができる文章で、それを結構よく読んでましたね。映画ってこうやって撮るのかと。
Q:今までのお話と全然逆方向な現場なわけですね。
諏訪敦彦:ゴダールはね、だからあんまり会いたくないですね、ゴダールには(笑)。
Q:でもやっぱりジャン=ピエール・レオーさんとやることで、楽しいというのは変ですけれども、民主的なというか、自分でやりたい現場になるんじゃないかなっていう予感はあったんですか?
諏訪敦彦:それはまた別ですね、レオーを見て感じたのはいわゆる普通の演技というか、役者というのは、ジャン=ピエール・レオーの前は、僕が見ていたものでいうと、アメリカニューシネマの時代なんです。だから『イージー・ライダー』(69)よりは後ですけど『タクシードライバー』(76)ぐらいまでの10年間の映画っていうのがあって、ここで新しい俳優っていうのが出てきた。ダスティン・ホフマンとかアル・パチーノとか、アクターズスタジオ系で非常にリアル、こういう人いるよね、ニューヨークに、みたいな、そういうものを作り出すことが出来る人達。一方、ジャン=ピエール・レオーっていうのは、ああいう人は絶対にいない、どこにもこんな人いないでしょ、嘘でしょみたいな、嘘でしょっていうのはおかしいですけど、現実を再現しようとは思ってないわけです、何か人に別のものを信じさせようとしていない。それはゴダールの映画もそう。トリュフォーの映画はずっとロマネスクな方に向かっていくわけですけど、ゴダールはそれを破壊していく。結局、映画を撮ってますよ僕達という、そういう現実を隠さない。だから『勝手にしやがれ』(59)で、シャンゼリゼの街でばーっと撮るじゃないですか、そうするとみんな振り返るんですよね、カメラを。アメリカ映画では、そういうことが起きないわけです。映画撮ってますってことを隠す、カメラがありますよっていうのは隠す、普通そうですけど。だけど映画撮ってますっていうのを隠さない、僕達は映画作ってるんだぞっていうことを隠さない映画ですね。映画を観てる間は本当にあるかのように信じさせるっていうのが、フィクション映画なんですけど、これはディズニーランドみたいなもので、ディズニーランドにいる間は千葉にいることを忘れさせるっていうのがフィクション映画の機能なわけですね。ゴダールの映画は、でも千葉だよっていうのを見せちゃう。ということは、僕達のこの現実と映画は繋がっているって思えるわけです。そういう存在なんですね、ジャン=ピエール・レオーって。だから、カメラの前で緊張しながら演技してるんです。ゴダールに、これやれって言われてずっと電話かけてるとか、そういうことが明らかになっていく、それはなんか自分達を映画の制作現場に逆に引きずり込んでいくっていうところがあって、自分もその映画を作ることに参加しうる、映画を作ることは自分と無関係じゃないと思えたと思うんです。
Q:現実と映画を地続きにするための存在というか。
諏訪敦彦:そういうことが魅力的にできちゃう存在というか、まるで踊っているような演技をする。特別でしたね。
Q:可愛いですね。
諏訪敦彦:まあそうですね、可愛らしいと思いますよ、子どもですよね、普通の大人じゃないです。


| ←前ページ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 次ページ→ | |
